「うちの子、いつまで指吸いしてるんだろう…」
「このままじゃ歯並びが悪くなっちゃう?」
この記事は、そんな 0歳~5歳のお子さんの指吸いに悩む親御さん に向けて書いています。
指吸いの原因から、年齢別の対策、専門家への相談まで、あなたの悩みを解決できる情報 をギュッとまとめました。
この記事を読めば、指吸いに関する不安が解消され、お子さんの成長をサポート できるようになりますよ!
なぜ指吸いするの? 年齢別の原因をチェック!
指吸いの原因は、お子さんの年齢によって様々です。まずは、お子さんの年齢に合わせた原因を知ることから始めましょう。
0歳~2歳:
この時期の指吸いは、成長の過程でよく見られる行動です。
- 吸啜反射(きゅうてつはんしゃ): 生まれたばかりの赤ちゃんは、口に触れるものを吸う反射を持っています。これは自然な行動なので、無理にやめさせる必要はありません。
- 探索行動: 手の動きが活発になるにつれて、自分の手を口に入れて感覚を学ぼうとします。
- 情緒安定: 不安や緊張を和らげるために指を吸うことがあります。眠い時、退屈な時、お腹が空いた時などに見られます。
- 口の機能発達: 生後12ヶ月頃までに指や物をしゃぶることは、目と手の協調運動を促し、味や形を覚えるために必要な行為です。

3歳~5歳:
3歳を過ぎても指吸いが続く場合は、少し注意が必要です。
- 習慣化: 5歳以上で指吸いをしている場合は、癖になっている可能性が高くなります。
- 寂しさや不安: 眠気が来たとき、寂しい気持ちを抱えているときに指吸いをすることが多いです。
- ストレス: 幼稚園などの環境にうまく適応できないことが原因となる場合があります。
- 環境の変化: 社会性の芽生え、学校生活の準備、友達との関わり方を覚えることなど、新たな生活適応能力が求められることでストレスを感じていることも。
医学的な原因:
まれに、医学的な原因で指吸いをすることがあります。
- 亜鉛不足は皮膚炎、脱毛、味覚障害、発育障害、性機能不全、食欲低下、下痢、骨粗しょう症、キズの治りが遅い、感染しやすくなるなどの症状を引き起こす可能性があります。
- 指吸いの原因として考えられる可能性は低いですが、気になる場合は専門家への相談を検討しましょう。
指吸いをしやすい状況:
どんな時に指吸いをしているか観察してみましょう。
- 0歳~2歳:眠い時、不安な時、退屈な時、お腹が空いた時。
- 3歳~5歳:夜、寝かしつけが必要なく一人で眠る場合に、一人でいるために指吸いをしてしまう。
- 1歳~2歳頃の指しゃぶりは退屈なときや眠いときに出やすい。
- 眠たい時、甘えたい時、遊びに飽きた時などにする。
FAQ:うちの子、もしかしてストレス?
Q:3歳の子どもが幼稚園に行き始めてから、指吸いをするようになりました。ストレスが原因でしょうか?
A:環境の変化は、お子さんにとって大きなストレスになることがあります。幼稚園での出来事を聞いてあげたり、一緒に遊ぶ時間を作ったりして、安心させてあげましょう。
指吸いの影響|知っておくべきリスク
指吸いは、放置すると様々な影響を及ぼす可能性があります。ここでは、指吸いが与えるリスクについて解説します。
身体的な影響:
一番気になるのは、歯並びへの影響ですよね。
- 歯並びへの影響:
- 下の歯並びがガタガタになったり、出っ歯になったり、上下の歯が噛み合わなくなる可能性があります。
- 乳歯が生えそろいはじめてからの指しゃぶりは、まだ形成途中の顔の骨格や歯の成長に影響をおよぼし、不正咬合につながる可能性がある。
- 指をくわえる力によって上の前歯は上前方に押し出され、下の前歯は後下方へと押さえつけられた状態になる。
- 5歳頃に指吸いを続けていると、歯並びや顎への影響が考えられます。
- 指への影響: 2~3歳を過ぎても指に「吸いダコ」ができるほどしつこく指しゃぶりを続けている場合は、やめさせる必要性があります。頻繁に指をしゃぶる子どもは皮膚炎になることもあるため注意が必要です。

心理的な影響:
指吸いは、心の状態と深く関わっています。
- 長時間指しゃぶりをする癖が続くと、歯並びだけでなく、顔貌にも変化が表れてコンプレックスになる可能性。
- 無意識の指しゃぶりには、ストレスや不安から逃げて安心感を得たいという心理がかかわっている場合がある。
- 新しい環境や未知の状況に直面したとき、安心感を求めて指を口に運ぶ。
言語発達への影響:
発音にも影響が出ることもあります。
- 前歯の噛み合わせが悪くなることで、サ行、タ行、ラ行の発音が難しくなり、舌足らずな話し方になる。
- 口を閉じにくくなり、口呼吸になる。
【年齢別】指吸い対策:今日からできること
年齢別に、今日からできる指吸い対策をご紹介します。焦らず、お子さんのペースに合わせて、根気強く取り組んでいきましょう。
0歳~1歳未満:
この時期は、無理にやめさせる必要はありません。
- 無理にやめさせず、見守る。
- 授乳は時間をかけて乳児が満足するまで抱く。
- 寝る前にたっぷり授乳をする、スキンシップをとるなど、赤ちゃんがリラックスして眠れるように工夫する。
1歳~2歳:
遊びや声かけで、自然と指吸いを減らしていきましょう。
- 寝付くまでは手をつなぐ。お子様が眠くなってしまった時に優しく握ってあげることで、愛情表現で安心感を与えながら指を口に入れないようにする方法です。
- 手袋や靴下を手にはめる。手袋や指にテーピングをして指しゃぶりが難しい環境にするのも1つの方法です。指人形をつくり、子どもと遊びながら指しゃぶりをやめるように伝えるのも良いです。
- 指しゃぶりに関する絵本を読む。指しゃぶりの本を何度も読み聞かせをすることで、子どもが内容を記憶し、「指しゃぶりはいけない」と自分自身で気づく可能性があります。
- 眠たい時、甘えたい時、遊びに飽きた時などにする場合は、気をそらすための工夫をする。
3歳~:
言葉で伝え、理解を促すことが大切です。
- 「指吸いをやめようね」と声かけをする。
- 指吸いをしなければ褒める。
- 退屈な生活環境が原因とみられる場合は、他のものに意識を向けさせるため、積み木やパズルなど、手を動かすおもちゃで一緒に遊ぶと効果的。
- 不安による指しゃぶりが原因の場合は、寝る前に手を握ってあげたり、絵本を読み聞かせたり、スキンシップの回数を増やして、不安を取り除いてあげると、リラックスする。
- 4歳以上の子供の指しゃぶりは、家庭や幼稚園・保育園などで何らかのストレスを抱えている可能性。心を落ち着かせるために指しゃぶりをする癖が習慣化していると考えられる。
共通の対策:
年齢に関わらず、生活習慣を見直すことが大切です。
- 生活のリズムを整え、外遊びをさせ、家の中でも指を使って遊ぶ機会を増やすようにする。寝付くまでの間、子どもの手を握って指をマッサージしてあげる。
- 二人目の子どもが産まれると上の子が赤ちゃんのように指しゃぶりをすることがありますが、これは意識して上の子と向き合う時間をつくれば解決できるでしょう。
- 体をよく動かさせる。
- 眠りにつくまで一緒にいる。
- 眠るときに指吸いをしていたらそっと外す。
4. 指吸いグッズの効果と選び方
指吸い対策には、様々なグッズがあります。お子さんに合ったグッズを選んで、楽しく指吸い卒業を目指しましょう。
- 指サック、指人形、手袋など
-
市販のアイテムを利用する。
- 苦味成分配合のマニキュア
-
歯科では、舐めると苦い口にしても問題ないマニキュアのようなものを指に塗ることがある。
あわせて読みたい 【もう悩まない!】指しゃぶり卒業への最短ルートは「かむピタ」!先輩ママも大絶賛 「うちの子、いつまで指しゃぶりするんだろう…」 「色々な方法を試したけど、全然効果がない…」 2歳~6歳のお子さんの指しゃぶりに悩んでいるママ・パパ、もしかしてあ…
【もう悩まない!】指しゃぶり卒業への最短ルートは「かむピタ」!先輩ママも大絶賛 「うちの子、いつまで指しゃぶりするんだろう…」 「色々な方法を試したけど、全然効果がない…」 2歳~6歳のお子さんの指しゃぶりに悩んでいるママ・パパ、もしかしてあ… - 安全ガード付乳歯歯ブラシ
-
生後6ヶ月以降、のどを突く心配がなく、安心して使用できる。
- おしゃぶり
-
指しゃぶりよりも止めやすく、歯並びにも影響が少ない。ただし、歯並びの悪化や、言葉を話す機会が少なくなるなどマイナスの面も否定できません。
- えほん
-
「ゆびたこ」子ども達がこぞってゆびたこを嫌いになる話。
 ポチップ
ポチップ
選び方のポイント:
- 安全性: 素材の安全性(BPAフリー、食品グレードなど)を確認しましょう。
- 年齢: 対象年齢を確認しましょう。
- 指吸いの程度: お子さんの指吸いの程度に合ったものを選びましょう。
- 装着感: お子さんが嫌がらず、快適に装着できるものを選びましょう。
- 耐久性: 繰り返し使える、丈夫なものを選びましょう。
- 手入れのしやすさ: 清潔に保てる、手入れが簡単なものを選びましょう。
専門家への相談も検討しよう
「色々試したけど、なかなか指吸いが止まらない…」
そんな時は、専門家への相談も検討してみましょう。
- 相談するタイミング:
- 5歳以上になっても指吸いを続けている場合。
- 深く悩んでいる場合。
- お子さんの歯並びに心配な様子がある場合。
- 相談できる専門家:
- 歯科医、矯正歯科医、小児歯科医
- 小児科医
- 児童家庭支援センター、子育て支援センター、保健センター、自治体の子育て相談窓口
- 相談のポイント:
- お子さんの年齢、指吸いの頻度、状況などを詳しく伝えましょう。
- 気になること、不安なことを遠慮なく質問しましょう。
- 専門家のアドバイスを参考に、家庭でできることを実践しましょう。
- 専門家の探し方:
- インターネットで検索する。
- 口コミサイトを参考にする。
- かかりつけの病院に紹介してもらう。
指吸いを卒業した体験談と成功の秘訣
最後に、指吸いを卒業したお子さんの体験談をご紹介します。先輩ママ・パパの経験から、ヒントをもらっちゃいましょう!
成功の秘訣:
- 焦らず、根気強く取り組む。
- お子さんの気持ちに寄り添う。
- 家庭環境を整える。
- ご褒美を用意する。
- 周りの人に協力してもらう。
指吸い卒業は、お子さんにとって大きな成長のチャンスです。
この記事が、あなたとお子さんの指吸い卒業をサポートする一助となれば幸いです。
最後に
また、ご自身の体験談や質問があれば、コメント欄にお気軽にお寄せください。
みんなで情報を共有して、指吸い卒業を応援しましょう!
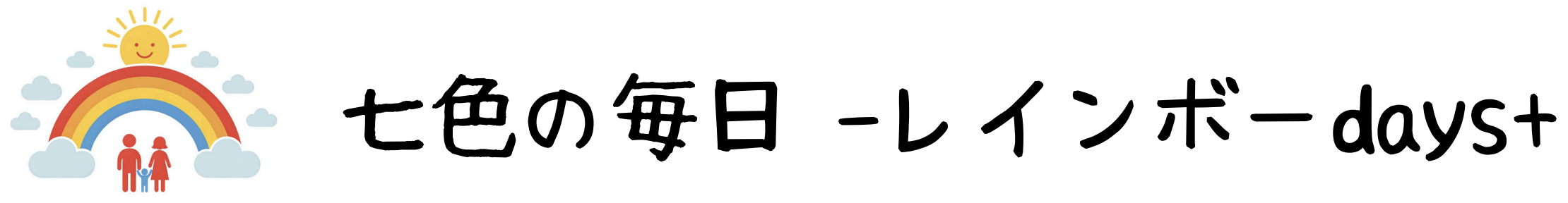













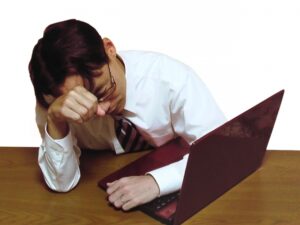
コメント