初めての育児、お疲れ様です!夜泣きで悩んでいませんか?
「いつまで続くの…?」
「何をやっても泣き止まない…」
そんな不安な気持ち、すごくよく分かります。この記事は、そんな頑張るパパ・ママのために、夜泣きの原因から具体的な対策、おすすめグッズまでをまとめた完全ガイドです。
専門家監修のもと、少しでも安心して育児に取り組めるよう、役立つ情報をお届けします。
夜泣きはいつから始まる?月齢別の目安とサイン
夜泣きって何?
夜泣きに医学的な定義はありません。一般的には、赤ちゃんが夜中に突然泣き出したり、なかなか泣きやまない状態を指します。
多くの育児書では、生後半年頃から1歳半くらいの赤ちゃんに見られる、夜間の理由がわからない泣きとされています。
夜泣きはいつから始まるの?
一般的に、夜泣きは生後5~6ヶ月頃から本格的に始まります。早い子では生後3~4ヶ月頃から始まることも。
生後8~10ヶ月頃にピークを迎え、1歳~1歳半頃に落ち着くことが多いようです。
夜泣きのサインを見逃さないで!
- 夜中に何度も起きる
- 夜中に激しく泣く

なぜ夜泣きするの?主な原因と背景
夜泣きの原因は、実はまだはっきりと解明されていません。でも、いくつかの要因が考えられています。
夜泣きのメカニズム
- 睡眠サイクルの未熟さ: 赤ちゃんの睡眠サイクルは大人のように安定していません。浅い眠りの時に目が覚めやすいんです。
- 脳の発達のアンバランス: 本能的な欲求を司る部分が先に発達し、我慢などを司る部分の発達が遅れるためと言われています。
- 昼間の刺激の処理: 昼間の刺激を脳が処理しきれず、夜中に泣いてしまうことも。
考えられる要因はたくさん!
夜泣きの原因は一つではありません。様々な要因が複雑に絡み合っていると考えられています。
- 生理的な要因:
- 部屋の暑さ・寒さ
- お腹が空いた
- おむつが汚れている
- 鼻が詰まっている
- どこかが痛い
- 布団の肌触りがイヤ
- 心理的な要因:
- 初めての場所や人・新しい経験などの刺激
- 怖い思い
- 不安や寂しさ・甘えたい気持ち
- その他の要因:
- 日中の運動不足
- 保育園の開始や引っ越しなど環境の変化
- 体調不良
- 歯が生え始める
【タイプ別】夜泣きの原因と具体的な対策
赤ちゃんによって夜泣きの原因は様々。ここでは、タイプ別の原因と対策をご紹介します。
睡眠リズムの乱れタイプ
- 原因: 体内時計が未発達で、昼夜の区別がつきにくい。
- 対策:
- 朝は7時までに起こし、太陽の光を浴びさせる。
- 昼間はお散歩や外遊びで身体を動かす。
- 夕方5時以降は昼寝を控える。
- 夜は遅くとも8時までに寝かせることを目標にする。
- 寝る前30分は部屋を暗くして、絵本を読んだりスキンシップをとる。
環境要因タイプ
- 原因: 部屋の温度や湿度、明るさなどが不快。
- 対策:
- 室温は夏場26~28℃、冬場20~22℃に保つ。
- 湿度は50~60%に保つ。
- 部屋を暗くする。
寝かしつけの習慣タイプ
- 原因: 抱っこや授乳で寝かしつける習慣がついている。
- 対策:
- 赤ちゃんが夜中に起きた時に、就寝時と同じ環境・状態にする。
- 抱っこや授乳で寝かしつける習慣をやめる。
運動不足タイプ
- 原因: 日中の運動量が不足している。
- 対策:
- 日中は外で遊んだり、スポーツをする。
夜泣きで困ったら?すぐに試せる7つの対処法
何をしても泣き止まない…そんな経験、ありますよね。
そんな時に試せる、すぐにできる対処法をご紹介します。
- 抱っこ、トントン、子守唄:
安心感を与え、落ち着かせる効果があります。 - 添い寝、添い乳:
ママの温もりを感じることで安心します。 - ホワイトノイズ、音楽:
胎内音に近い音や、リラックスできる音楽を流す。 - 部屋を暗くする:
刺激を減らし、眠りやすい環境を作る。 - 温度・湿度を調整する:
快適な環境を整える。 - おしゃぶり、ガーゼ:
口に何かを含ませることで安心する。 - 絵本を読む:
落ち着いた声で語りかけることで安心する。
ポイント!色々な方法を試してみて、お子さんに合った対処法を見つけてあげてくださいね。

夜泣きはいつ終わる?卒業の兆候と親ができること
夜泣きはいつか必ず終わります!終わりの時期や兆候を知っておくことで、少し気持ちが楽になりますよ。
終わる時期の目安
一般的に、夜泣きは1歳~1歳半頃に落ち着きます。でも、個人差は大きいので、2歳を過ぎても時々夜泣きをする子もいます。
夜泣き卒業の兆候
- 夜中に起きる回数が減る
- 泣かずに自分で寝付く
- 睡眠時間が長くなる
親ができること
一番大切なのは、焦らないこと!
- 焦らず、おおらかな気持ちで向き合う。
- 夜泣きは成長の過程だと理解する。
- 夫婦で協力して乗り越える。
専門家からのアドバイス:夜泣きと向き合う心構え
夜泣きは、親にとって本当に大きな負担となります。一人で悩まず、誰かに相談することも大切です。
親の心のケアが最優先!
- 一人で悩まず、家族や友人、専門機関に相談する。
- 睡眠不足にならないよう、できるだけ休息をとる。
- 完璧を求めすぎず、適度に手を抜く。
- 夜泣きは親のせいではないと理解する。
専門家への相談も検討しましょう
子どもの健康状態が心配な場合は、かかりつけの小児科や、子どもの睡眠を見てもらえる小児神経科などへ受診するのもいいでしょう。
最後に
夜泣きは本当に大変な時期ですが、必ず終わりが来ます。この記事が、少しでもあなたの育児の助けになることを願っています。応援しています!
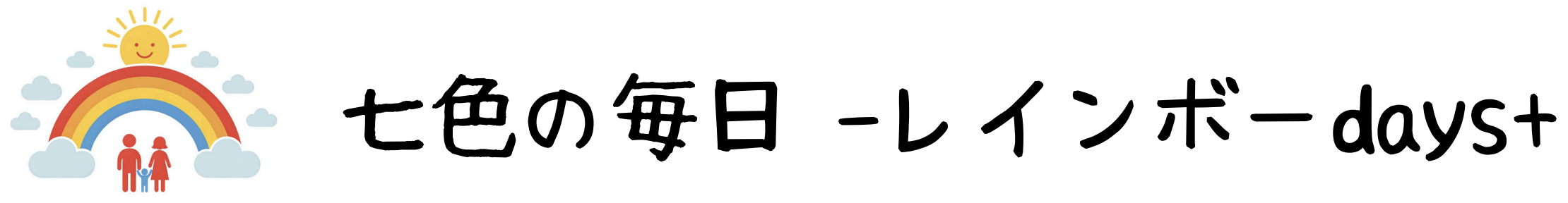


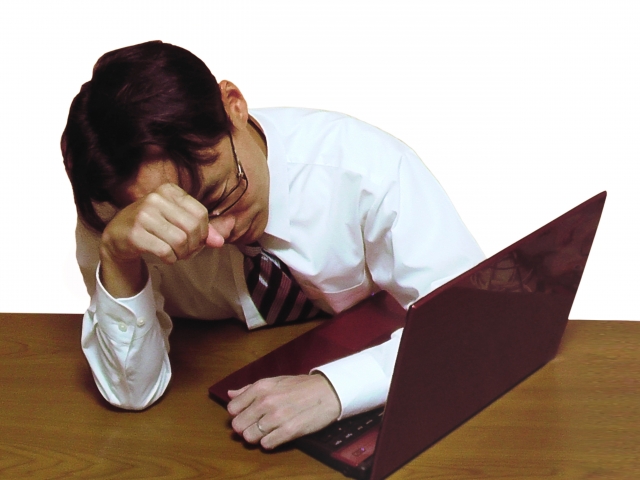





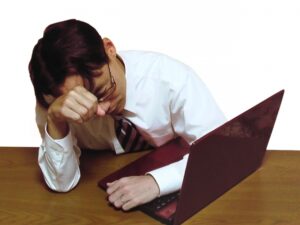

コメント