「キーッ!」「ギャー!」突然始まる子どもの奇声に、毎日イライラしていませんか?
もしかしてうちの子だけ?どうして奇声を発するの?
そんな悩みを抱えるあなたに向けて、この記事では、
- 奇声の原因
- 年齢別の特徴
- 具体的な対応策
をわかりやすく解説します。
この記事を読めば、奇声への理解が深まり、少しでも穏やかな気持ちで子育てできるようになるはずです。ぜひ最後まで読んでみてくださいね。
なぜ?子どもの奇声に隠された理由
子どもの奇声に悩む親御さんは少なくありません。
「キーッ」という叫び声や「うわあああ」という叫び声など、その種類も様々です。
奇声の原因を理解することで、より適切な対応ができるようになります。
発達段階と奇声の関連性
生後数ヶ月から5歳頃にかけては、言葉での表現が難しいため、感情や欲求を声に出して表すことがあります。
多くの場合、奇声は子どもの成長過程で自然に現れる感情表現の一つです。
成長の過程で徐々におさまっていく傾向にあり、必ずしも心配する必要はありません。
言葉をしっかり話せる年齢になっても奇声が続く場合は、他の発達に関するサインと合わせて考える必要があります。
おおよそ3歳を過ぎるまでは、その行動が発達障害によるものなのか否かの判断はつきにくいです。
5歳を超えても改善しない場合は医師への相談を検討しましょう。
奇声の種類と意味合い
奇声の種類としては、「キーッ」という叫び声や「うわあああ」という叫び声などが挙げられます。
奇声は、
- 喜び、興奮
- フラストレーション
- ストレス
- 不安
- 注意を引きたいという
を示すことがあります。
特に機嫌が悪いわけでもなさそうなのに奇声を発する場合もあります。
参考書籍
子育てアドバイザー・おやのめぐみ先生の著書『お母さんが変われば、子どもの「イライラ行動」が変わる!』(PHP研究所)は参考になるでしょう。
年齢別に見る奇声の原因と特徴
年齢によって奇声の原因が異なる場合があります。
お子さんの年齢に当てはめて、原因を探ってみましょう。
0~1歳
- 要求を伝えたい(お腹が空いた、おむつを替えてほしいなど)
- 不安が大きい時(知らない人や場所への戸惑い)
- 眠い、疲れた(たそがれ泣き)
- 声を出すのが楽しい(5~6ヶ月頃、聴覚が発達し自分の声が認識できるようになる)
- 注目してほしい、周囲の反応を試したい
2~3歳
上記0~1歳に加えて、
- 上手く言葉にできない
- 感情の表現方法がわからない
- うまく体が動かせない
などの要因があります。
イライラするのは私だけ?奇声で悩む親御さんの声
SNSなどでは、多くの方が子どもの奇声に悩んでいることがわかります。
具体的な例として、以下のような声があります。
- 「電車の中での奇声が本当に困る。周りの目が気になるし…」
- 「スーパーで突然奇声をあげて、恥ずかしい思いをした」
また、同居の両親を持つ人が、父親の奇声や母親の文句に悩まされている例もあります。
子育ては孤独になりがちですが、同じように悩んでいる人はたくさんいます。
一人で抱え込まず、SNSや育児フォーラムなどで悩みを共有してみるのも良いでしょう。

今すぐできる!奇声への具体的な対応策
奇声への対応策は、年齢や状況によって異なります。
0~1歳
- 要求を理解し、言葉で伝える
- 「しー」のポーズで静かにする場所を教える
- 不安を取り除くために抱きしめる
- リラックスできる環境を作る(電気をつける、好きなおもちゃ、抱っこなど)
- 生活リズムを整える(早寝早起き、午睡)
- 奇声以外の遊びを提示する
- 集中して向き合う時間を作り、褒める
- 毎日の行動に一定の習慣をつける
2~3歳
- できる範囲でやりたいことに挑戦させる
- 上手くできない時は補助し、できたところを褒める
- 気持ちを代弁し、落ち着かせる(「〇〇したかったんだね」「上手くいかなかったんだね、それは悔しかったね」など)
- 具体的な方法や言葉を伝える
- 大声を出してはいけない理由を根気強く教える
- 「静かにしなさい!」と怒鳴りつけたり、「いい加減にしなさい!」という言葉で叱ることは避ける
外出時に突然奇声を発するケース(特に電車内)では、事前に遊び方を決めておく、お気に入りのおもちゃを持参するなどの対策が考えられます。

【年齢別の対応ヒント】
- 2歳: 共感的な言葉がけで、気持ちを受け止めてあげましょう。「〇〇したかったんだね」と代弁してあげるのも効果的です。
- 3歳: 奇声の代わりにできる行動を提案してみましょう。「大声で叫ぶ代わりに、絵を描いてみようか?」など、代替案を示してあげると、子どもも理解しやすいです。
専門家からのアドバイス:発達心理学の視点
奇声が続く場合、発達障害の可能性も考慮する必要があります。
決して不安を煽るわけではありませんが、早期発見・早期療育は大切です。
発達障害との関連性
奇声は発達障害のある子どもたちに見られる行動の一つです。
奇声と関連する可能性のある発達障害として、ASD(自閉スペクトラム症)、ADHD(注意欠陥/多動性障がい)、LD(学習障がい)が挙げられています。
- ASD(自閉スペクトラム症)
-
過剰な刺激に対する反応や、感覚過敏による不快感から奇声を発することがあります。言葉でのコミュニケーションが難しいため、奇声を発して自分の感じていることを表現することも。
- ADHD(注意欠陥/多動性障がい)
-
衝動性が高く、感情や行動の制御が困難なため奇声を発することがあります。集中力が短いため、注意を引くために無意識に奇声を上げることも考えられます。
- LD(学習障がい)
-
フラストレーションやストレスを感じた際に、感情をコントロールするのが難しく、奇声をあげることがあるかもしれません。特に、言語表現に困難を持つ子どもは、自分の思いをうまく伝えられずに奇声を発することで感情を表現する場合がある。
療育に関する情報
奇声をあげる行為が発達障害によるものである場合、専門家の助けを借りて療育を行うことが重要です。
児童発達支援センターや放課後等デイサービスなどを利用し、子どもの特性に合わせた支援を受ける。
専門家による適切な指導は、子どもの感情や行動のコントロールを助け、社会的な適応能力を高めることにつながる。
奇声が続く場合は?相談できる窓口と支援
「もしかしてうちの子は…?」と不安になったら、一人で悩まずに専門機関に相談してみましょう。
相談窓口リスト
- 子育て支援センター:地域の子育てに関する相談に乗ってくれます。
- 児童相談所:子どもの福祉に関する専門的な相談ができます。
- 保健センター:発達に関する相談や、専門機関の紹介をしてくれます。
療育ネットでは、放課後等デイサービスの開業をサポートしています。
発達障害のある子どもたちに特化したサービスを提供することで、彼らの社会的自立を支援し、家族に対してもレスパイトケアとしての役割を果たすことができます。
【親御さんメンタルケアも大切です】
子どもの奇声に毎日付き合うのは、本当に大変なことです。
イライラしてしまうのは、決してあなただけではありません。
- 深呼吸をする
- 好きな音楽を聴く
- アロマを焚いてリラックスする
など、自分なりのリラックス方法を見つけて、心に余裕を持つように心がけましょう。
夫婦で協力し、子育ての負担を分担することも大切です。

まとめ
子どもの奇声には、様々な原因があります。
年齢や発達段階、状況に合わせて適切な対応をすることで、奇声は改善していく可能性があります。
もし、奇声が続くようであれば、専門機関に相談することも検討しましょう。
何よりも大切なのは、お子さんと向き合い、愛情を持って接することです。
子育ては大変ですが、お子さんの成長を一緒に見守っていきましょう。
(記事の最後に、読者への応援メッセージと、他の子育て記事へのリンクを挿入)
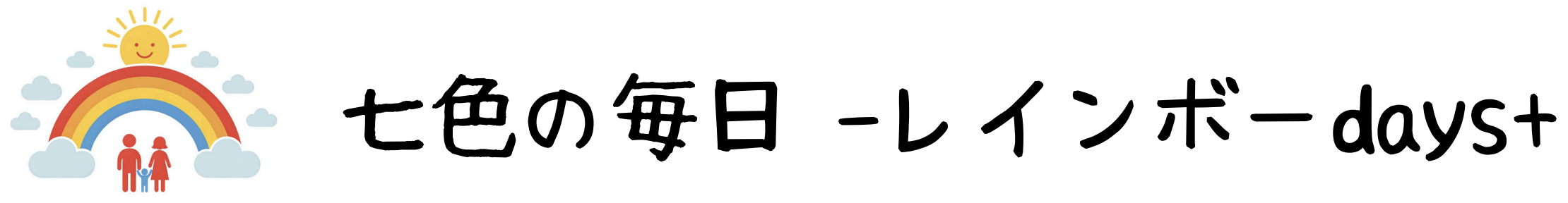




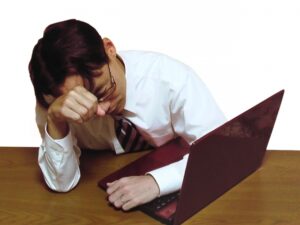

コメント